この記事の目次
近年、健康志向やエコ意識の高まりにより、天然素材からできた建材の「リノリウム」が注目を集めています。
リノリウムは有害物質を出さないため安全性が高く、環境に配慮したサステナブルな素材です。
一方、クッションフロアや塩ビタイルなどの床材は耐久性やデザイン面で人気が高く、住宅や公共施設で幅広く採用されています。
それぞれの床材には、どのような特徴があるのでしょうか?
本記事では、リノリウムの特徴やメリット、デメリット、クッションフロアや塩ビタイルとの違いについて詳しく解説します。
リノリウムとは?
リノリウムは、1860年代にイギリスのフレデリック・ウォルトンが発明した建築素材です。亜麻仁油やジュート、松油、石灰などの天然素材を用いています。
日本に伝わったのは1920年頃で、当時は公共施設や軍艦の材料として使用されていました。クションフロアや塩ビタイルなどの床材の登場により需要が減っていたものの、高い安全性と環境へ配慮可能な点が評価され、また注目されています。
リノリウムの歴史と発明背景
リノリウムは、1860年代、イギリスのフレデリック・ウォルトンによって発明されました。
ウォルトンは、亜麻仁油を長期間放置すると酸化してゴム状の物質になることを発見し、この酸化亜麻仁油をベースとした新しい床材の開発に着手。亜麻仁油にコルク粉や木粉などの天然素材を混ぜ、ジュート麻などの基布に圧着し、耐久性と柔軟性を兼ね備えた床材を生み出しました。
この革新的な床材は、現代に至るまで幅広く受け入れられるようになりました。国内では、1920年に東リ株式会社(旧・東洋リノリユーム株式会社)が国内初のリノリウム製品を完成させています。
リノリウムが今再注目されている理由
リノリウムが再注目されている理由は、環境と身体に優しいからです。リノリウムはカーボンニュートラルな素材です。製造時に二酸化炭素を多少排出しますが、原材料(植物)のときは空気中の二酸化炭素を吸収しています。つまり、排出量と吸収量はプラスマイナスゼロで、環境に負荷をかけていません。その上、生物分解性もあり、土に埋めると自然にかえります。
リノリウムは、ドイツや北欧諸国を中心とした環境保全に力を入れている国からも高く評価されています。
また、主原料の亜麻仁油は、大腸菌O-157やA型インフルエンザに対して抗菌・抗ウイルス作用があります。さらに、静電気が発生しにくい性質も持っています。ほこりがつきにくいうえ、ハウスダストが除去しやすいため、アレルギー体質の方におすすめです。
天然素材で構成される環境に優しい床材
リノリウムは、その主成分が亜麻仁油、石灰岩、松ヤニ、コルク粉、麻布といった天然素材である点が大きな特徴です。
・亜麻仁油…亜麻の種子から抽出される油で、リノリウムの柔軟性と耐久性を高める役割を果たす
・石灰岩…粉砕して炭酸カルシウムとして使用され、リノリウムの強度を向上させる。
・松ヤニ…松から採取される樹脂で、接着剤としての役割を持つ。
・コルク粉…コルク樫の樹皮を粉砕したもので、クッション性と断熱性をもたらす。
・麻布…ジュート麻などを織った布で、リノリウムの基布として使用される。
これらの天然素材は、製造過程での環境負荷が低く、廃棄後も自然に還る理由から、環境に優しい床材として評価されています。
内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?
現代のリノリウムの特徴
天然素材でつくられたリノリウムは、有害物質が発生しないため、シックハウス症候群の発症やアレルギーがある方でも安心して使用できます。
主成分の亜麻仁油には抗菌・抗ウイルス効果があるだけでなく、酸化作用によって空気中のアンモニア臭を脱臭する効果もあるため、トイレの床材としてもおすすめです。
耐用年数は約30~40年と長く、適切なメンテナンスを行えば、さらに長く使用できます。
デザインも豊富で、ナチュラルな雰囲気からモダンな空間まで幅広く対応しています。
表面は滑りにくく、適度な柔軟性があるため、歩行音が静かで足への負担も少ない点が特長です。
一方で、紫外線に弱く、日当たりのよい場所だと変色する恐れがあります。
亜麻仁油特有のニオイがあるため、人によっては苦手に感じることもあるでしょう。
ニオイは時間の経過とともに薄れていくので、気になる方は定期的に換気を行うことをおすすめします。
リノリウムは天然素材を使用しており、原料の調達や製造に手間やコストがかかるため、ビニール製の床材に比べ価格が割高な傾向があります。
デザイン性の向上と豊富なカラーバリエーション
現代のリノリウムは、かつてのイメージを覆すほどデザイン性が向上しており、豊富なカラーバリエーションが展開されています。色数は50色以上あり、単色だけでなく大理石模様や木目調、抽象的なデザインなど、多彩な柄パターンが存在するのも特徴です。
さまざまなインテリアスタイルに合わせやすく、住宅だけでなく店舗やオフィス、公共施設など、幅広い空間で使用されています。
内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?
リノリウムとクッションフロア、塩ビタイルの違いは?

リノリウムは先ほどからお伝えしている通り、天然素材で作られた床材です。一般的に使われているクッションフロア、塩ビタイルとの違いについて解説します。
素材から見る3種類の床材の違い
リノリウムやクッションフロア、塩ビタイルは、それぞれ異なる素材で構成され、特徴も大きく異なります。それぞれの特徴について、以下の表にまとめました。
| 素材構成 | 環境性能 | 耐久性 | |
| リノリウム | 亜麻仁油、石灰岩、松ヤニ、コルク粉、麻布などの天然素材 | 環境負荷が低く、持続可能性がある | 適切なメンテナンスを行えば30〜40年という長い製品寿命が期待できる |
| クッションフロア | 塩化ビニルを主成分とするシート状の床材 | 製造過程でエネルギーを消費し、廃棄時にはダイオキシンなどの有害物質を排出する可能性がある | リノリウムと比較すると耐久性は劣る場合がある |
| 塩ビタイル | 塩化ビニルを主成分とするタイル状の床材 | クッションフロアと同じだが、製造過程での環境負荷を低減する技術が開発されており、リサイクル技術も進歩 | リノリウムと同程度の耐久性を持つ |
クッションフロアとは?
クッションフロアは、塩化ビニル(PVC)を主成分とするシート状の床材です。表面の塩化ビニル層と、クッション性を高める発泡層との多層構造が一般的です。
クッション性があるため、足触りが柔らかく、遮音性にも優れています。また、水に強いため、洗面所やトイレなどの水回りでの使用に適しています。デザインも豊富で、施工が比較的容易なので、一般住宅に広く普及している床材です。
塩ビタイルとは?
塩ビタイルは、塩化ビニルを主成分としたタイル状の床材です。クッションフロアと同様に塩化ビニル製ですが、タイル状のためデザインの自由度が高く、高級感のある空間を演出できます。
また、塩ビタイルは耐久性が高く、店舗やオフィスなど、人の出入りが多い場所でも使用されるのが特徴です。施工には接着剤を使用しますが、最近では裏面に粘着剤が付いたタイプもあり、DIYでも比較的簡単に施工できます。
リノリウムは、天然素材でありながら高い耐久性を持ち、長期間の使用に耐えることが可能です。一方、塩ビタイルは、合成樹脂の特性から特に耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れており、メンテナンスもしやすいです。
どちらがより耐久性が高いかは、どのような種類の摩耗や汚れに対して耐久性を求めるかによって異なります。日常的な使用における傷や汚れへの強さ、メンテナンスの手間などを考慮して、適切な床材を選ぶと良いでしょう。
内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?
リノリウムのメリット
リノリウムの主なメリットとして以下の4つが挙げられます。
・有害物質の心配がない
・抗菌作用が期待できる
・耐久性が高い
・静電気が発生しにくい特性がある
それぞれのメリットについてくわしく解説します。
有害物質の心配がない
リノリウムは化学物質が含まれていない安全性の高い素材です。化学物質が含まれている建材を使用すると、シックハウス症候群を引き起こすおそれがあります。発症すると、頭痛や吐き気、めまいといった症状が出ます。
抗菌作用が期待できる
リノリウムの主成分である亜麻仁油には、天然由来の成分として抗菌性が期待されています。一般的に、黄色ブドウ球菌や大腸菌などに対して抑制的に働く可能性があるとされており、衛生管理が重視される医療施設や学校などで選ばれる理由の一つです。
耐久性が高い
リノリウムは、適切なメンテナンスを行えば製品寿命が30〜40年続くのがメリットです。耐摩耗性や耐衝撃性にも優れており、傷やへこみがつきにくいという特徴も持ち合わせています。これにより、商業施設など、人の出入りが多い場所での使用実績も豊富です。
さらに、耐摩耗性や耐衝撃性にも優れており、傷やへこみがつきにくいという特徴も持ち合わせています。リノリウムは、適度なクッション性があるため、歩行時の衝撃を吸収し、足腰への負担を軽減する効果も期待できるでしょう。
静電気が発生しにくい特性がある
リノリウムは、静電気が発生しにくい特性も持っています。これは、リノリウムがわずかに導電性を持つのが理由です。
静電気は、電子機器の誤作動の原因となるため、コンピューター室やサーバー室など、精密機器を扱う空間の床材としても適しています。
内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?
リノリウムのデメリット
リノリウムの主なデメリットとして以下の3つが挙げられます。
・人によってニオイが気になる
・施工業者が限られる場合がある
・アルカリ性のものや紫外線に弱い
いずれも天然素材であることが要因です。
人によってニオイが気になる
リノリウムは、主成分である亜麻仁油特有の香りがする場合があります。この香りは、製造過程で亜麻仁油が酸化する際に発生するもので、健康は害さないものの、人によっては不快に感じる場面があります。
とはいえ、リノリウムの独特なニオイは時間の経過とともに自然に減少していくのがほとんどです。こまめな換気や消臭対策により、ニオイを早く解消できます。
施工業者が限られる場合がある
リノリウムの施工には、専門的な知識と技術が必要です。特に、シート状のリノリウムを継ぎ目なく美しく仕上げるには、熟練した職人の技術が求められます。
こうした事情から、リノリウムは一般的な工務店で対応できない場合があり、リノリウムの施工を専門とする業者に依頼する必要があります。専門業者を探す際には、施工実績などを確認すると良いでしょう。
アルカリ性のものや紫外線に弱い
リノリウムは、アルカリ性と紫外線に弱い性質があります。どちらも変色の原因になります。洗剤やワックスを使用する際は、かならず中性タイプのものを選びましょう。また、窓辺の紫外線対策も忘れずに行なってください。
内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?
リノリウムの入手方法と国内主要メーカー
リノリウムは、ホームセンターなどではほとんど取り扱っておらず、専門の床材販売店や施工店を通じて購入するのが一般的です。
日本国内で入手できる主要メーカーとしては、オランダのフォルボ社が挙げられます。フォルボ社の「マーモリウム」は、豊富なカラーバリエーションと高い品質で、日本国内でも広く採用されています。価格帯は6,600円〜8,200円/㎡(税別)です。
※2025年4月現在
国内で取り扱いのある主なリノリウム製品は、ファルボ社のマーモリウムなどがあります。
ファルボ社のマーモリウムは、天然素材を主成分としたリノリウム床材の代表的なブランドです。豊富なカラーとデザイン、優れた耐久性が特徴です。国内では、建材や床材を多く取り扱うTAJIMA(田島ルーフィング)が取り扱っています。
これらのメーカーのリノリウムは、専門の床材販売店やリフォーム業者などを通じて購入可能です。価格帯は、一般の床材に比べてやや高めですが、その分、耐久性やデザイン性に優れています。
内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?
リノリウムを取り入れる際の注意点

リノリウムの取り扱いには、注意しなければならないポイントが3つあります。
掃除用洗剤は中性洗剤を選ぶ
アルカリ性洗剤の例としては、重曹やセスキ炭酸ソーダなどが挙げられます。一方、中性洗剤としては、一般的な家庭用洗剤や、リノリウム専用のクリーナーなどが市販されています。
リノリウム専用ワックスを選ぶ
リノリウムのメンテナンスには、ワックスの使用も有効です。ただし、一般的なフローリング用ワックスではなく、リノリウム専用のワックスを選ぶ必要があります。
リノリウム専用ワックスには、半樹脂系ワックスや水性ポリマータイプなどがあり、リノリウムの表面を保護し、汚れや傷をつきにくくする効果があります。
ワックスがけの際は、古いワックスの劣化を防ぐために、すべてのワックスを剥がす作業が必要です。リノリウム専用の中性剥離剤を使用し、その後に専用ワックスを上塗りしましょう。
紫外線対策を行う
リノリウムは紫外線を受けると変色するおそれがあります。UVカットガラスにして、なるべく室内に紫外線を取り込まないようにしましょう。
UVカット機能のついたカーテンやロールスクリーンでも対策できます。
家具の設置による傷防止策
リノリウムの床に家具を設置する際には、傷防止の対策が必要です。
たとえば、家具の脚にフェルトやゴムなどの保護材を取り付ければ、床への傷つきを軽減できます。重量のある家具を移動させる際には、直接引きずらず、毛布などを敷いて滑らせるようにしましょう。
万が一床に傷がついてしまった場合には、専用の補修キットなどで修復できます。
内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?
リノリウムのテーブル天板としての活用法
リノリウムは、床材としてだけでなく、テーブルの天板としても活用できるのが特徴です。
テーブル天板にリノリウムを使用するメリットとしては、以下の点が挙げられます。
・筆記性…適度なクッション性があり、文字が書きやすい
・耐久性…傷や汚れに強く、長く使える
・デザイン性…豊富なカラーバリエーションで、インテリアに合わせやすい
このほかにも、指紋がつきにくかったり、帯電防止効果でホコリが溜まりにくかったりと、さまざまなメリットもあります。木のようにぬくもりが感じられる素材なのも、嬉しいポイントといえるでしょう。
家具用リノリウム(ファニチャーリノリウム)の特徴
家具用リノリウム(ファニチャーリノリウム)は、一般的な床材用リノリウムとは異なり、テーブル天板などの家具用途に特化して作られています。
主な特徴としては、以下の点が挙げられます。
・厚み…一般的なリノリウム床材は2.5mm程度だが、2mm程度の厚みが主流
・柔軟性…曲げやすく、天板の形状に合わせて加工しやすい
・専用接着剤…家具用リノリウムの接着には、専用の接着剤を使用
抗菌、抗ウイルス、脱臭、抗アレルギー性に優れている点から見ても、安心して取り入れられる素材です。
テーブル天板に最適な厚みと色選び
リノリウムを使用した天板の家具を選ぶなら、厚みは2.0mm〜2.5mm程度が最適です。この厚みであれば、十分な耐久性と筆記性を確保できます。
色選びは、色褪せしにくい色調を選びましょう。濃い色は色あせが目立ちやすいため、淡い色や中間色がおすすめです。
天板の色に迷うなら、テーブルの使用目的に合わせて選んでみましょう。
【例】
・ダイニングテーブル…食事が美味しそうに見える暖色系
・ワークテーブル…集中しやすい落ち着いた色
・子供用テーブル…汚れが目立ちにくい色(黒など)
DIYでテーブルにリノリウムを貼る方法
DIYでテーブルにリノリウムを貼る際には、いくつかの道具と手順が必要です。
まずは、次のようなアイテムを用意します。
・カッター
・接着剤
・ローラー
・正確な寸法を測るための定規
・接着剤を均一に塗布するためのヘラ
作業を始める前に、天板の表面をきれいにしましょう。汚れや油分を取り除き、表面が平らであることを確認してください。もし凹凸がある場合は、パテなどで平らにする必要があります。
次に、リノリウムの貼り付け手順についてです。
①リノリウムを天板よりも少し大きめにカット
②接着剤を天板とリノリウムの両面に均一に塗布
③接着剤が乾く前に、リノリウムを天板に貼り付け、ローラーを使ってしっかりと圧着
(この際、空気が入らないように注意深く作業を進めるのが大切です)
貼り付け後、はみ出した部分をカッターで丁寧にカットします。最後に、天板の端を保護し、見た目を良くするために、木口テープなどを貼ると良いでしょう。
内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?
よくある質問
リノリウムの欠点は何ですか?
リノリウムの主な欠点は、以下の通りです。
・初期費用が高めである
・亜麻仁油特有のにおいがする場合がある(時間経過で軽減)
・紫外線で変色する可能性がある
・アルカリ性洗剤で劣化するため、中性洗剤での掃除が必要な
リノリウムは劣化しますか?
リノリウムは、適切なメンテナンスを行えば、30〜40年という長い製品寿命が期待できます。耐久性が高く、長期間使用できる床材といえるでしょう。
しかし、経年変化で色あせや傷などが発生する可能性があります。劣化を最小限に抑えるには、定期的なワックスがけや、汚れを放置しないなどのメンテナンスが重要です。
内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?
家づくりのご相談は”ロゴスホーム”へ
ロゴスホームは、日本一寒いとされる過酷な地でも快適に過ごせる技術とノウハウを持っているハウスメーカーです。高機密・高断熱をはじめ、誰もが快適に過ごせる住宅が建てられると自負しています。
リノリウムを用いた事例も多数ございます。興味のある方は、お気軽にロゴスホームへお問い合わせください。
失敗したくない方へ

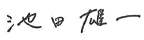

知りたかったたった
1つのこと

手に入れる方法
内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?
リノリウムの総まとめ
リノリウムは、亜麻仁油などの天然素材を主成分とした、環境に優しい床材です。抗菌作用や耐久性に優れ、デザイン性が高い点も特徴です。リノリウムのメリットとしては、快適な歩行感や豊富なカラーバリエーションが挙げられます。一方、価格が高く、においが気になる点はデメリットといえるでしょう。
他の床材との違いとしては、天然素材である点や、耐久性が高いなどが挙げられます。床材としてはもちろん、テーブル天板などにも使用できます。
購入の際は、アルカリ性洗剤の使用を避ける、またリノリウム専用のワックスを使用するなど、注意点も理解しなくてはなりません。リノリウムを入手したい方は、専門の床材販売店や施工業者に相談しましょう。










