この記事の目次
「和室の畳をおしゃれなフローリングに変えたいけど、どうすればいいの?」「DIYで簡単にできる方法はある?費用はどれくらいかかるの?」
この記事では、そんなお悩みを持つあなたのために、畳の部屋をフローリングにするための様々な方法、気になる費用、そしてDIYの手順や注意点まで、分かりやすく解説します。畳からフローリングへの変更は、お部屋の印象をガラリと変え、掃除のしやすさやインテリアの自由度を高めるなど、多くのメリットがあります。
特に、「畳 フローリング 敷くだけ」といった手軽な方法から、本格的なリフォームまで、あなたの希望や予算に合わせた最適なプランが見つかるはずです。この記事を読めば、畳の部屋を快適なフローリング空間に変えるための具体的なステップが明確になり、理想のお部屋づくりをスムーズに進めることができるでしょう。
畳からフローリングにする方法
畳の部屋をフローリングに変える方法は、大きく分けて2つあります。手軽にDIYできる「敷くだけ」の方法と、本格的な「リフォーム工事」です。それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況や希望に合った方法を選びましょう。
「敷くだけ」で簡単DIY
「敷くだけ」で畳をフローリングにするのは、最も手軽で費用を抑えられる方法です。特別な工具や技術がなくても、比較的簡単に施工できるのが魅力です。
- フローリングカーペットやウッドカーペットを利用する
畳の上に直接敷くだけで、あっという間にフローリング調の床に変えられます。賃貸物件で原状回復が必要な場合や、一時的に部屋の雰囲気を変えたい場合に最適です。 - フロアタイルやクッションフロアを敷く
カッターナイフなどで比較的簡単にカットでき、デザインも豊富なため、DIY初心者にも人気があります。部分的な貼り替えも可能です。
これらの方法は、大掛かりな工事が不要で、費用も比較的安く済むのが大きなメリットです。また、元の畳を傷つけにくいため、賃貸住宅にお住まいの方でも安心して試すことができます。
本格的なリフォーム工事
本格的なリフォーム工事では、既存の畳を撤去し、下地処理を行った上でフローリング材を施工します。仕上がりの美しさや耐久性を重視する方、部屋の段差を解消したい方におすすめの方法です。
- 畳を撤去し、床下地を調整する
畳を剥がし、床の高さを調整したり、断熱材を入れたりする作業が含まれます。 - フローリング材を施工する
無垢フローリングや複合フローリングなど、様々な種類のフローリング材から選んで施工します。
この方法は、床材の選択肢が広く、防音性や断熱性を高めることも可能です。ただし、専門的な知識や技術が必要となるため、DIYで行うのは難易度が高く、業者に依頼するのが一般的です。費用や工期も「敷くだけ」の方法に比べてかかります。
内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?
畳からフローリングへの費用
畳からフローリングへの変更にかかる費用は、選択する方法(DIYか業者依頼か)や部屋の広さ、使用する材料によって大きく変わります。ここでは、それぞれの費用相場や費用を抑えるポイントについて解説します。
DIYの場合の費用相場
DIYで畳をフローリングにする場合の費用は、主に材料費となります。選ぶ材料によって価格は変動しますが、比較的安価に抑えることが可能です。
- フローリングカーペット・ウッドカーペット
6畳あたり約1万円~5万円程度が目安です。素材や厚み、デザインによって価格差があります。 - フロアタイル
6畳あたり約2万円~6万円程度が目安です。接着剤が必要なタイプと不要なタイプがあります。 - クッションフロア
6畳あたり約1万円~4万円程度と、比較的安価なものが多いです。
その他、カッターナイフやメジャー、両面テープなどの細かな道具代も考慮しておきましょう。
業者依頼の場合の費用相場
業者に畳からフローリングへのリフォームを依頼する場合、材料費に加えて施工費や諸経費がかかります。本格的なリフォームの場合、畳の撤去費用や下地調整費用も含まれます。
- 畳を撤去し、一般的な複合フローリングに張り替える場合
6畳あたり約10万円~20万円程度が相場と言われています。 - 無垢フローリングなど高品質な素材を選ぶ場合や、床暖房を設置する場合
費用はさらに高くなる傾向があります。
正確な費用を知るためには、複数の業者に見積もりを依頼し、内容を比較検討することが重要です。
6畳・8畳の費用目安
部屋の広さによって費用は変動します。ここでは、代表的な広さである6畳と8畳の場合の費用目安をまとめました。
- 6畳の場合
- DIY(敷くだけタイプ):約1万円~6万円
- 業者依頼(本格リフォーム):約10万円~20万円
- 8畳の場合
- DIY(敷くだけタイプ):約1.5万円~8万円
- 業者依頼(本格リフォーム):約13万円~25万円
これはあくまで目安であり、使用する素材のグレードや工事内容によって費用は上下します。「畳 から フローリング 費用 6 畳」などで検索すると、より具体的な事例が見つかることもあります。
費用を抑えるポイント
畳からフローリングへの変更費用を少しでも抑えたいと考えるのは当然です。ここでは、費用を抑えるためのいくつかのポイントをご紹介します。
- DIYに挑戦する
「敷くだけ」タイプであれば、DIYで施工することで施工費を大幅に節約できます。 - 材料選びを工夫する
アウトレット品やセール品を利用したり、比較的安価な素材(クッションフロアなど)を選んだりすることで、材料費を抑えられます。 - 複数の業者から見積もりを取る(業者依頼の場合)
最低でも2~3社から見積もりを取り、価格だけでなく工事内容や保証内容もしっかり比較しましょう。 - リフォーム時期を検討する
業者の閑散期を狙うと、割引交渉がしやすくなる場合があります。 - 補助金や減税制度を確認する
自治体によってはリフォームに関する補助金制度がある場合や、一定の条件を満たせば税金の控除を受けられる場合があります。お住まいの自治体の情報を確認してみましょう。
これらのポイントを参考に、賢く費用を抑えながら理想のフローリング空間を実現しましょう。
内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?
DIYで畳をフローリングにする手順
「畳 を フローリング に DIYしたいけど、具体的にどうすればいいの?」という方のために、ここでは代表的な「フローリングカーペット」と「フロアタイル」を使ったDIYの手順を解説します。
必要な道具と材料リスト
DIYを始める前に、必要な道具と材料を揃えましょう。
- 共通で必要なもの
- メジャー(部屋の寸法を正確に測るため)
- カッターナイフ(大きめのものが使いやすい)
- カッターマット(床を傷つけないため)
- 軍手(ケガ防止)
- 掃除機(畳の上のゴミやホコリを取り除くため)
- 雑巾
- フローリングカーペットの場合
- フローリングカーペット本体
- フロアタイルの場合
- フロアタイル本体
- (必要に応じて)フロアタイル用接着剤、ヘラ
- (必要に応じて)ゴムハンマー(タイルをしっかり圧着するため)
- 定規(直線カットのため)
材料を購入する際は、部屋のサイズよりも少し大きめに用意しておくと、失敗したときや調整が必要な場合に安心です。
フローリングカーペット敷設手順
フローリングカーペットは、畳の上に敷くだけで完了する最も簡単な方法です。
- 畳の掃除
まず、畳の上のゴミやホコリを掃除機で丁寧に取り除きます。必要であれば固く絞った雑巾で拭き掃除をしましょう。畳が湿っている場合は、しっかり乾燥させてから作業を開始してください。 - 部屋の採寸
部屋の正確なサイズを測ります。柱や壁の凹凸がある場合は、その部分も細かく測定しましょう。 - フローリングカーペットの準備
購入したフローリングカーペットを広げ、部屋のサイズに合わせてカットが必要な場合は、裏面からカッターナイフで慎重にカットします。 - 敷設
部屋の隅からフローリングカーペットを敷き詰めていきます。複数枚に分かれているタイプの場合は、つなぎ目が目立たないように丁寧に合わせます。 - 調整
敷き終わったら、浮いている部分やズレがないか確認し、必要であれば調整します。
これで、あっという間に畳の部屋がフローリングに変わります。
フロアタイル設置の手順
フロアタイルは、ピース状のタイルをパズルのように組み合わせて敷き詰めていく方法です。
- 畳の掃除と準備
フローリングカーペットと同様に、畳の上をきれいに掃除し、乾燥させます。畳の凹凸が気になる場合は、薄い合板などを敷いて下地を平らにすると、よりきれいに仕上がります。 - 部屋の採寸と割り付け
部屋のサイズを測り、フロアタイルをどのように配置するか(割り付け)を計画します。部屋の中央から敷き始めるか、壁際から敷き始めるかなどを決めます。 - フロアタイルのカット
壁際や柱周りなど、そのままでは収まらない部分は、フロアタイルをカットして調整します。カッターナイフで表面に数回切り込みを入れ、折り曲げるようにすると比較的簡単にカットできます。 - 敷設(接着剤不要タイプの場合)
裏面に滑り止め加工がされているタイプや、はめ込み式のタイプは、そのまま畳の上に並べていくだけです。 - 敷設(接着剤使用タイプの場合)
畳の上に直接接着剤を塗布するか、フロアタイルの裏面に接着剤を塗布し、順番に貼り付けていきます。接着剤がはみ出さないように注意しましょう。 - 圧着
タイルを敷き終わったら、ゴムハンマーやローラーなどで軽く叩いたり押さえたりして、しっかりと圧着させます。
フロアタイルはデザインが豊富なので、自分好みの空間を作りやすいのが魅力です。
DIYの注意点と失敗しないコツ
DIYで畳をフローリングにする際には、いくつか注意しておきたい点があります。これらを押さえておけば、失敗を防ぎ、より満足のいく仕上がりを目指せます。
- 正確な採寸が最も重要
部屋の寸法を間違えると、材料が足りなくなったり、逆に余りすぎてしまったりします。必ず複数回測り、正確な数値を把握しましょう。 - 畳の湿気対策を忘れずに
畳の上に直接フローリング材を敷く場合、畳とフローリング材の間に湿気がこもり、カビやダニが発生する可能性があります。防湿シートを敷いたり、定期的な換気を心がけたりすることが大切です。 - 下地の状態を確認する
畳が大きく沈み込んだり、傷みが激しい場合は、そのまま上に敷くとフローリング材が不安定になったり、早期に劣化したりする可能性があります。必要であれば、畳の補修や交換、または下地調整を検討しましょう。 - 無理のない計画を立てる
DIYに慣れていない場合は、いきなり広い範囲に挑戦するのではなく、小さなスペースから試してみるのも良いでしょう。また、作業時間には余裕を持ちましょう。 - 安全に作業する
カッターナイフなどを使用する際は、軍手を着用し、ケガに十分注意してください。 - 原状回復の確認(賃貸の場合)
賃貸物件の場合は、どこまでのDIYが許可されているか、退去時の原状回復義務について、事前に大家さんや管理会社に必ず確認しましょう。
焦らず丁寧に作業を進めることが、DIY成功の秘訣です。
内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?
畳の上に敷くフローリングマット・材
畳の上に敷くだけで手軽に洋室化できるフローリングマットやフローリング材は、種類も豊富です。それぞれの特徴を理解し、お部屋の用途や好みに合わせて選びましょう。
フローリングマット・カーペット
フローリングマットやフローリングカーペットは、ロール状や折りたたみ式で販売されており、広げて敷くだけで簡単に施工できるのが最大の特徴です。
- メリット
- 施工が非常に簡単で、DIY初心者でも扱いやすい。
- 比較的安価な製品が多い。
- 取り外しが容易なため、賃貸物件でも使いやすい。
- 一時的な模様替えにも適している。
- デメリット
- 本格的なフローリング材に比べると、質感や耐久性で劣る場合がある。
- 薄手のものは、下の畳の感触が伝わりやすいことがある。
- サイズが合わない場合、カットが必要。
「畳 フローリング マット」や「フローリング マット 畳 の 上」で検索すると、様々な製品が見つかります。
ウッドカーペット
ウッドカーペットは、木材や木目調の素材で作られたカーペット状の敷物です。フローリングカーペットの一種ですが、より本物の木に近い質感が特徴です。
- メリット
- 本物のフローリングに近い見た目と質感を得られる。
- 敷くだけで簡単に施工できる。
- 比較的耐久性が高いものもある。
- デメリット
- 重量があるため、一人での設置が大変な場合がある。
- フローリングマットに比べると価格が高めになる傾向がある。
- 折り曲げられないため、搬入経路の確認が必要。
「畳 の 上 に 敷く フローリング マット」として、ウッドカーペットは人気の選択肢です。
フロアタイル
フロアタイルは、塩化ビニルなどの素材で作られた正方形や長方形のタイル状の床材です。デザインやカラーバリエーションが豊富で、組み合わせ次第で個性的な空間を演出できます。
- メリット
- デザイン性が高く、石目調や木目調などリアルな質感を再現したものが多い。
- 耐久性や耐水性に優れている製品が多い。
- 汚れた部分だけを交換できる。
- カッターナイフで比較的簡単にカットできる。
- デメリット
- 施工に手間と時間がかかる場合がある(特に接着剤を使用するタイプ)。
- 製品によっては、下の畳の凹凸を拾いやすいことがある。
- フローリングカーペットに比べると価格が高めになる傾向がある。
「畳の上 フローリングマット」として、デザイン性を重視する方におすすめです。
クッションフロア
クッションフロアは、塩化ビニル素材のシート状の床材で、クッション性があるのが特徴です。水に強く、キッチンやトイレなどの水回りにもよく使われます。
- メリット
- 比較的安価で、手軽に導入しやすい。
- 耐水性が高く、汚れも拭き取りやすいのでメンテナンスが楽。
- クッション性があるため、足腰への負担が少なく、防音効果も期待できる。
- カッターナイフやハサミで簡単にカットできる。
- デメリット
- 重い家具を長期間置くと跡がつきやすい。
- 熱に弱いものがある。
- 本格的なフローリング材に比べると、質感は劣る。
掃除のしやすさやコストパフォーマンスを重視する方に向いています。
各マット・材の比較と選び方
どの製品を選べば良いか迷ってしまう方のために、それぞれの特徴を比較し、選び方のポイントをまとめました。
| 種類 | 施工の容易さ | 価格帯(6畳目安) | 耐久性 | デザイン性 | メンテナンス性 | おすすめな人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フローリングマット・カーペット | ◎ | 1~5万円 | △ | 〇 | 〇 | とにかく手軽に、安く済ませたい人、賃貸で一時的に使いたい人 |
| ウッドカーペット | 〇 | 2~6万円 | 〇 | ◎ | 〇 | 本格的な木の質感を求める人、ある程度の耐久性が欲しい人 |
| フロアタイル | △ | 2~6万円 | ◎ | ◎ | ◎ | デザインにこだわりたい人、耐久性やメンテナンス性を重視する人、DIYを楽しみたい人 |
| クッションフロア | ◎ | 1~4万円 | △ | 〇 | ◎ | コストを抑えたい人、水回りにも使いたい人、クッション性や防音性を求める人 |
選ぶ際のポイント
- 予算はどれくらいか?
- DIYにどれくらい手間をかけられるか?
- どんな部屋の雰囲気にしたいか?(デザイン性)
- 耐久性やメンテナンスのしやすさはどの程度求めるか?
- 賃貸物件か持ち家か?(原状回復の必要性)
これらの点を考慮し、ご自身のライフスタイルや目的に最適な製品を選びましょう。
内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?
畳をフローリングにする注意点
畳からフローリングへの変更は魅力的な選択肢ですが、いくつか注意しておきたい点もあります。メリット・デメリットを理解し、後悔しないためのポイントを押さえておきましょう。
メリットとデメリット解説
畳からフローリングにすることで得られるメリットと、知っておくべきデメリットを整理しました。
- メリット
- 掃除が格段に楽になる
畳のように目にゴミが入り込むことが少なく、掃除機やフローリングワイパーで手軽に掃除できます。 - ダニやカビが発生しにくい
畳に比べて湿気を溜め込みにくいため、アレルギーの原因となるダニやカビの繁殖を抑えやすくなります。 - インテリアの自由度が広がる
洋風の家具やラグとの相性が良く、モダン、北欧風、ナチュラルなど、様々なテイストのインテリアを楽しめます。 - 家具の跡がつきにくい
畳のように重い家具を置いた跡が残りにくいです。(素材によります) - 部屋が広く見える効果も
フローリングの色や木目によっては、部屋全体がすっきりとし、広く感じられることがあります。
- 掃除が格段に楽になる
- デメリット
- 足元が冷えやすい
特に冬場は、畳に比べて床が冷たく感じられることがあります。 - 防音性が低下する可能性がある
畳には音を吸収する効果がありますが、フローリングにすると足音や物音が響きやすくなることがあります。特にマンションなど集合住宅の場合は注意が必要です。 - 畳特有の調湿効果が失われる
畳には室内の湿度を調整する機能がありますが、フローリングにはその効果は期待できません。 - 初期費用がかかる
特に本格的なリフォームの場合は、ある程度の費用が必要になります。 - 硬いため転倒時の衝撃が大きい
小さなお子さんや高齢の方がいるご家庭では、転倒時のケガのリスクを考慮する必要があります。
- 足元が冷えやすい
これらのメリット・デメリットを総合的に比較検討することが大切です。
後悔しないためのポイント
「畳 から フローリング 後悔」といった事態を避けるために、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 変更する目的を明確にする
「なぜフローリングにしたいのか?」を具体的にすることで、素材選びやリフォームの方向性が定まります。(例:掃除を楽にしたい、おしゃれな部屋にしたい、など) - ライフスタイルに合った素材を選ぶ
小さなお子さんやペットがいる場合は、傷つきにくく滑りにくい素材、アレルギー体質の方がいる場合は、低ホルムアルデヒドの素材などを検討しましょう。 - 防音性や断熱性を考慮する
特にマンションの場合は、階下への騒音対策として防音性能の高いフローリング材を選んだり、防音マットを併用したりすることを検討しましょう。また、床の冷えが気になる場合は、断熱材の使用や床暖房の導入も選択肢に入ります。 - 予算をしっかり計画する
材料費だけでなく、施工費や諸経費も考慮し、無理のない予算計画を立てましょう。 - 賃貸の場合は必ず規約を確認する
原状回復義務の範囲や、DIYの可否について、事前に大家さんや管理会社に確認することがトラブル回避につながります。 - サンプルを取り寄せて確認する
フローリング材の色や質感は、カタログやウェブサイトで見るのと実物では印象が異なることがあります。可能であればサンプルを取り寄せ、実際に見て触って確認しましょう。
これらのポイントを事前に検討することで、満足のいくリフォームが実現しやすくなります。
カビ・湿気対策と換気
畳の上に直接フローリング材を敷く場合、最も注意したいのがカビと湿気の問題です。畳は湿気を吸ったり吐いたりする調湿機能を持っていますが、フローリング材で覆ってしまうと、その機能が損なわれ、畳とフローリング材の間に湿気がこもりやすくなります。
- 対策方法
- 防湿シートの使用
畳とフローリング材の間に防湿シートを敷くことで、畳からの湿気がフローリング材に影響を与えるのを防ぎます。 - 定期的な換気
部屋の窓を開けて空気を入れ替えることで、室内の湿気を排出し、カビの発生を抑えます。特に梅雨時期や結露しやすい冬場は意識して行いましょう。 - 畳をしっかり乾燥させる
フローリング材を敷く前に、畳が十分に乾燥していることを確認してください。 - すのこ状の下地材の使用
畳とフローリング材の間に空間を作ることで、通気性を確保する方法もあります。 - 除湿器やサーキュレーターの活用
室内の湿度が高い場合は、除湿器を使用したり、サーキュレーターで空気を循環させたりするのも効果的です。
- 防湿シートの使用
カビは健康にも影響を与える可能性があるため、しっかりとした対策が必要です。
防音対策と床の冷え対策
フローリングにすることで、畳に比べて足音や物音が響きやすくなったり、床が冷たく感じられたりすることがあります。これらの対策も事前に検討しておきましょう。
- 防音対策
- 防音性能の高いフローリング材を選ぶ
LL値(床衝撃音レベル)が小さいものほど防音性能が高いとされています。 - 防音マットや遮音シートを敷く
フローリング材の下に敷くことで、音の伝わりを軽減できます。 - カーペットやラグを敷く
音を吸収する効果があり、部分的な対策として有効です。 - スリッパを履く
歩行音を軽減する効果があります。
- 防音性能の高いフローリング材を選ぶ
- 床の冷え対策
- 断熱材を入れる(本格リフォームの場合)
床下に断熱材を施工することで、床からの冷気をシャットアウトできます。 - 床暖房を設置する(本格リフォームの場合)
足元から暖かく、快適に過ごせます。 - 厚手のカーペットやラグを敷く
断熱効果があり、足元の冷えを和らげます。 - 厚手のスリッパやルームシューズを履く
手軽にできる冷え対策です。 - 断熱シートを敷く
フローリングの下やカーペットの下に敷くことで、冷気を遮断する効果が期待できます。
- 断熱材を入れる(本格リフォームの場合)
これらの対策を組み合わせることで、より快適なフローリング空間を実現できます。
賃貸物件での原状回復義務
賃貸物件で畳をフローリングに変更する場合、最も重要なのが「原状回復義務」です。退去時には、部屋を入居時の状態に戻す必要があるため、大家さんや管理会社に無断で本格的なリフォームを行うことはできません。
- 確認すべきこと
- 賃貸借契約書の内容
DIYや模様替えに関する規定を確認しましょう。 - 大家さん・管理会社への相談
どのような方法なら許可されるのか、事前に必ず相談し、許可を得るようにしましょう。
- 賃貸借契約書の内容
- 賃貸物件におすすめの方法
- 「敷くだけ」タイプのフローリングカーペットやフロアタイル
これらは畳を傷つけずに設置でき、退去時には簡単に撤去できるため、原状回復が容易です。 - 置き畳の上に敷く
畳を保護する意味でも有効です。
- 「敷くだけ」タイプのフローリングカーペットやフロアタイル
- 避けるべきこと
- 畳に直接接着剤を使用する
- 畳を剥がしてフローリングを施工する(無許可の場合)
- 釘やネジで固定する
トラブルを避けるためにも、必ず事前に確認と許可を取り、ルールを守ってDIYを楽しみましょう。
内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?
フローリングに畳を敷く選択肢
これまでは畳からフローリングへの変更について解説してきましたが、逆に「フローリング の上 畳」を敷きたいというニーズもあります。フローリングの洋室に、手軽に和の空間を取り入れたい場合に「置き畳」は便利なアイテムです。
置き畳の種類と特徴
置き畳とは、フローリングなどの床の上に直接置くだけで使える畳のことです。ユニット畳とも呼ばれ、様々な種類があります。
- 素材
- い草
伝統的な畳の素材で、独特の香りや調湿効果があります。 - 和紙
い草に比べて耐久性が高く、撥水加工が施されているものもあり、お手入れがしやすいのが特徴です。ダニやカビが発生しにくいというメリットもあります。 - 樹脂(ポリプロピレンなど)
水に強く、丸洗いできるものもあります。カラーバリエーションも豊富です。
- い草
- 形状・サイズ
- 正方形(琉球畳風)や長方形などがあり、サイズも様々です。
- 厚みも製品によって異なります。
- 縁(へり)の有無
- 伝統的な縁ありタイプと、モダンな印象の縁なしタイプ(琉球畳風)があります。
お部屋の雰囲気や用途に合わせて、最適な置き畳を選びましょう。
置き畳のメリット・デメリット
フローリングの上に置き畳を敷くことには、以下のようなメリットとデメリットがあります。
- メリット
- 手軽に和の空間を作れる
工事不要で、置くだけでくつろぎの和スペースが完成します。 - クッション性がある
フローリングに比べて柔らかく、座ったり寝転んだりするのに快適です。小さなお子さんのプレイスペースにも適しています。 - 調湿効果やリラックス効果(い草の場合)
い草の置き畳は、室内の湿度を調整したり、独特の香りでリラックス効果をもたらしたりします。 - 移動や収納が容易
軽量なものが多く、使わないときは簡単に片付けられます。 - 部分的な模様替えが可能
必要なスペースに必要な枚数だけ敷くことができます。
- 手軽に和の空間を作れる
- デメリット
- 段差ができる
フローリングとの間に段差が生じるため、つまずかないように注意が必要です。 - ズレやすい場合がある
裏面に滑り止め加工がされていないものは、動いているうちにズレてしまうことがあります。滑り止めシートなどを併用すると良いでしょう。 - フローリングとの間に湿気がこもる可能性
長期間敷きっぱなしにすると、フローリングと置き畳の間に湿気がこもり、カビの原因になることがあります。定期的に置き畳を上げて換気することが大切です。 - 「置き畳 デメリット」として、耐久性が低いものや、安価なものは質感が劣る場合があることも挙げられます。
- 段差ができる
これらの点を理解した上で、上手に活用しましょう。
フローリングマットとしての畳
置き畳は、フローリングの上に敷く「マット」のような感覚で使うこともできます。
- 子供のプレイスペースとして
クッション性があるので、子供が安全に遊べるスペースを作れます。 - くつろぎスペースとして
リビングの一角に敷いて、ゴロゴロできるリラックス空間を作るのも良いでしょう。 - 来客時の簡易的な寝具として
布団を敷く際に、床の硬さを和らげるために使うこともできます。 - ヨガやストレッチスペースとして
適度な硬さとクッション性があり、エクササイズにも向いています。
フローリングの便利さと畳の快適さを両立できるのが、置き畳の魅力です。
内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?
まとめ
この記事では、畳の部屋をフローリングにするための様々な方法、費用、DIYの手順、そして注意点について詳しく解説してきました。
畳からフローリングへの変更は、お部屋の機能性やデザイン性を大きく向上させる可能性を秘めています。
- 手軽さを重視するなら、「敷くだけ」のフローリングカーペットやフロアタイルがおすすめ。
- 本格的な仕上がりや耐久性を求めるなら、業者によるリフォームを検討しましょう。
- DIYに挑戦する場合は、正確な採寸と湿気対策が成功の鍵です。
- 費用を抑えたい場合は、材料選びを工夫したり、複数の業者から見積もりを取ったりすることが大切です。
- メリットだけでなく、デメリットや注意点(カビ、防音、冷え、賃貸の原状回復など)もしっかり理解しておきましょう。
また、逆にフローリングの上に「置き畳」を敷いて和の空間を作るという選択肢もご紹介しました。
「畳 フローリング」で検索しているあなたが、この記事を通して最適な方法を見つけ、理想のお部屋づくりを実現するための一歩を踏み出せることを願っています。ご自身のライフスタイルや予算、お部屋の状況に合わせて、じっくりと検討してみてください。
失敗したくない方へ

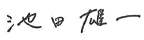

知りたかったたった
1つのこと

手に入れる方法
内観・外観イメージは具体的にお持ちでしょうか?
家づくりのご相談は”ロゴスホーム”へ
畳からフローリングへのリフォームをご検討中の方は、ぜひロゴスホームにご相談ください。
こだわり1:高品質であること
寒暖差が激しく地震も多い、日本で一番自然環境の厳しい地域といわれている十勝において「快適に過ごせる家」をつくることは特別な意味を持ちます。
● 高耐震で丈夫な2×6工法
● 高気密、高断熱
● 地震に強いベタ基礎工法
● 長期優良住宅に対応可能
● 下請け工務店を介さない直接施工
ロゴスホームの高品質な住宅性能は、これらのこだわりから成り立っています。
こだわり2:適正価格であること
ロゴスホームでは、値引きは一切いたしません。
適正価格でご提供しているからこそ、あえて大きめの金額を提示して後から「値引き」をするような不誠実なご提案の仕方はしていません。
すべてのお客様に、価格を抑えて良いものをご提供できるよう、透明性の高い料金システムでの家づくりに取り組んでいます。
こだわり3:パートナーであること
専門性の高い部門別のスタッフによる「チーム制」を導入し、各分野の専属スタッフが高いプロ意識をもって、より良いご提案にベストを尽くしています。
また、定期的なアフターメンテナンスをはじめ、お引き渡し後もお客様とのつながりを大切に「幸せな暮らし」を一緒につくるパートナーを目指しています。
お問い合わせはこちらからどうぞ▶ロゴスホーム










